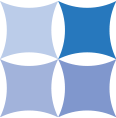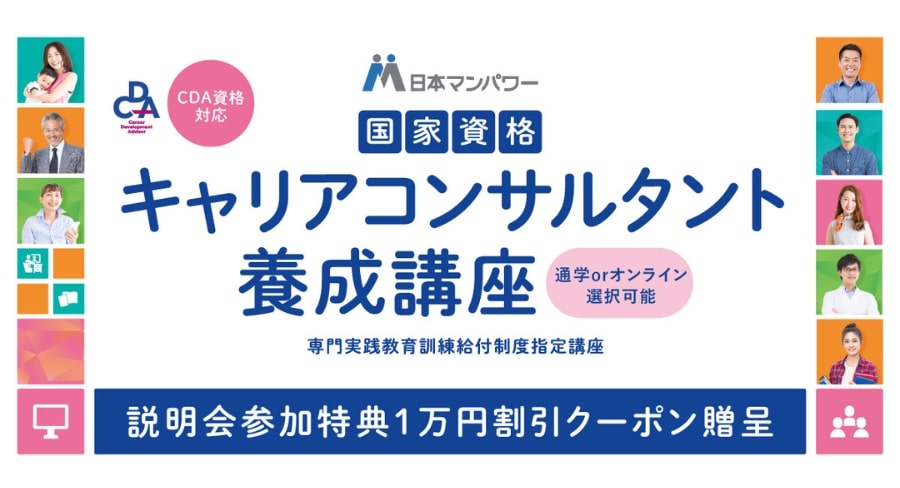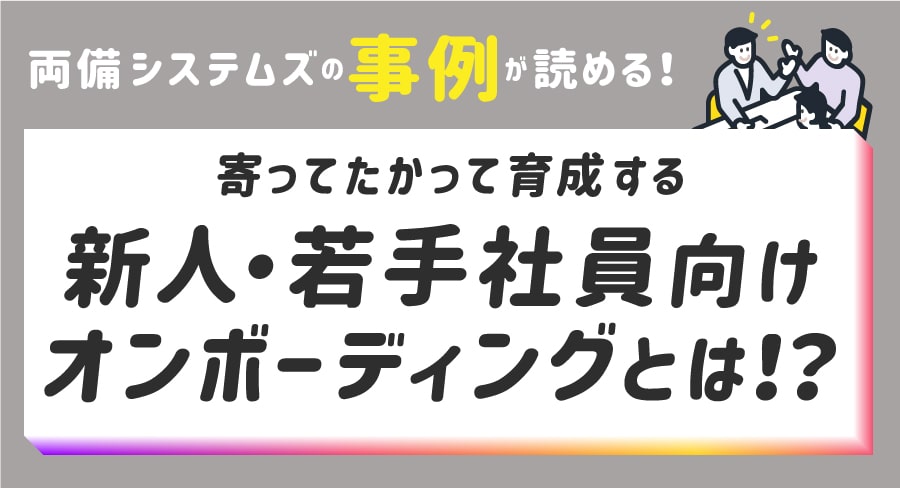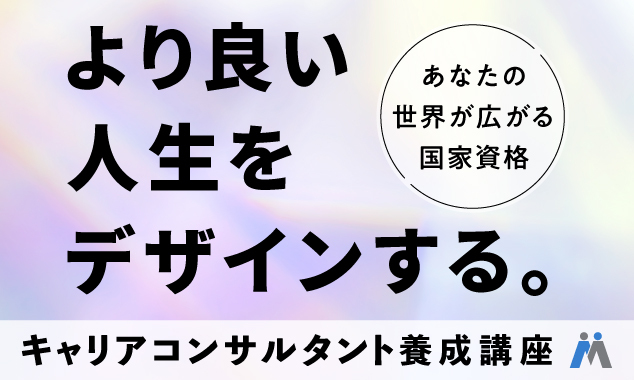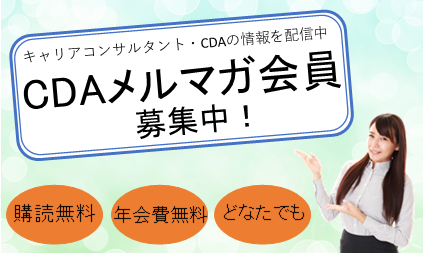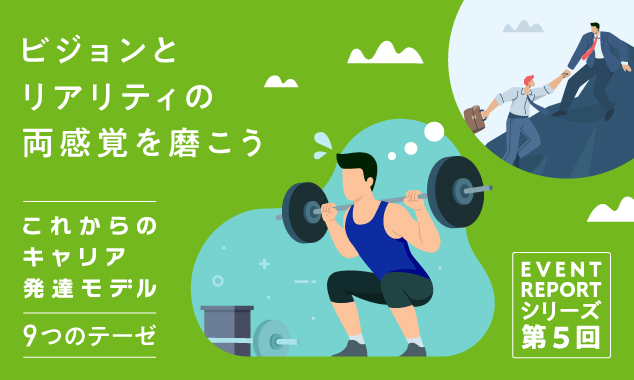
《これからのキャリア発達モデル イベントレポート》 第5回 ビジョンとリアリティの両感覚を磨こう
連載記事
2025.3.19
「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」の内容をご紹介するイベント第5回目。今回のテーマは、9つのテーゼの中の『ビジョンとリアリティの両感覚を磨こう』です。
ゲストはロバーツフリッツコンサルティングのチーフコンサルタント田村洋一氏。田村氏のお話の後、ロバートフリッツコンサルティング コンサルタントである森山千賀子氏、キャリアのこれから研究所メンバーを交えてパネルディスカッションを実施。
参加者同士のグループ対話や全体シェアも行い、全員でこのテーマを掘り下げる豊かな対話の時間となりました。
●イベント実施日 2024年12月23日
●「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」詳細ページは、こちら
●執筆:原博子 キャリアカウンセラー
●「これからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~」詳細ページは、こちら
●執筆:原博子 キャリアカウンセラー
1.主催者からの挨拶

キャリアのこれから研究所 所長 水野みち
ビジョンとは、理想の未来です。よく使われるものの、意外と深めて議論することは少ないと思います。ビジョンとは何か、ビジョンを描くというのは一体どういうことなのか。 そして同時に、自分自身が向かいたい先を描いたときに、今どこにいるのかという現在地、「リアリティ」に目を向けることもとても大切です。 改めて、ビジョンとは何か、どう描けばいいのか、そして現在地というのはどのように認識していけばいいのか。本日は、まさにこのテーマを長年深めてきた田村洋一先生からお話をいただきます。
本日は12月23日。年末の今、来年のビジョンというのを皆さんに考えていただく、とてもいいタイミングになるんじゃないかなとも思っております。
このような主催者水野の言葉のあと、本日のゲスト田村氏が登場しました。
2.田村洋一氏登場

田村洋一氏:ロバートフリッツコンサルティング チーフコンサルタント
田村:今日のテーマはビジョンとリアリティですが、皆さん自分のキャリアはどこに行くのか考える機会にしてもらえればと思います。 中にはすでに明確なビジョンを持っている、最初から持っているという稀有な人もいますよね。子供の頃から科学者になりたかった、プロ野球選手になりたかった、とかですね。そしてその道を作ってきた。 そのように努力と才能に恵まれてその道を突き進むというタイプの人も、もちろん世の中にはいます。
ビジョンが大事だ、と言われるので、ビジョンを持たないといけない、ビジョンがない自分はだめだと思い込んでしまう人もいます。 これは間違いだと思うんです。 ビジョンが明確な人というのは、そもそも珍しいのです。さて、皆さんはどうでしょうか?
3.田村氏のお話
(1)今日のテーマ 「リアリティが変わった時、どうする?」
田村:明確なビジョンを持っている人でさえ、途中で何が起きるかわからない。リアリティがどう変わるかわからない。その時どうするのか。今日のテーマはこれじゃないか、と思っています。
ビジョンを持つことが大事、無いよりはあった方がいい。それはそうかもしれません。 しかし、たいていの人は明確なビジョンなんて持ちようがないのです。 やりながら見つけるのです。最初から持っていて、そこを突き進んで幸せなキャリアを歩む人もいるかもしれませんが、多くの人はそうではない。 私もそうでした。 やっていくうちに、これは自分に合っているという仕事に巡り合うことがあるのです。
(2)田村氏のキャリアストーリー
田村:私の場合は社会人10年目の時に、ITとビジネスと英語ができるということを活かして外資系の銀行に転職しました。 そしたらもう…全く水が合わない。 10年近くITエンジニアとして勤めた最初の会社よりも働きにくい。非常に窮屈なところでした。
グローバルな会社でグローバルな仕事ができると思ったら、それは全くの幻想だった。大変ショックを受け、これは駄目だ、仕切り直そうと思って仕事を辞めようと思ったのですが、なかなか辞められませんでした
皆さんの中にも同じ経験をされている方もいらっしゃるかもしれません。もう先が見えない。今の仕事を心から楽しめない自分がいて、辞めようかな、でも辞めるためには次の行き先が必要だし、と時間が過ぎていく。そして辞めようと思っても組織の中で仕事をしていると、例えばマネージャーとして責任や関係性ができていて、今日辞めるわけにいかない、今月辞めるわけにいかない、と。
私の場合は、いよいよだと思ってから、さらに辞めるまでに半年かかりました。
私の場合は、いよいよだと思ってから、さらに辞めるまでに半年かかりました。
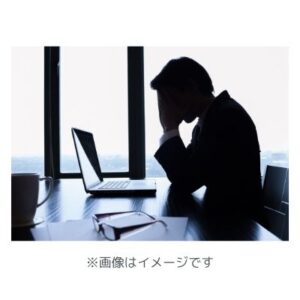
次は仲間と共に小さなベンチャーのスタートアップをやることにしたのです。しかし、そのベンチャーはすぐに潰れてしまいました。ショックでした。ただこれが、じつは私個人にとっては結果的に「とても良いこと」となったのです。 すっかりゼロになってしまったので、振り出しに戻って1から考えることができたのです。このことがきっかけで、戦略コンサルティング事務所に務めることになりました。1998年の春でした。
ここから今の仕事であるコンサルティング、コーチング、トレーニングといった仕事に繋がっていきました。つまり、失ってみることで、もう切羽詰まってどうするのか、自分は何が好きなのか何が得意なのか、どこに行きたいのか、ということをゼロから考え直すことを否応なくされたのです。すると、不思議なことに逆にチャンスが生まれたのです。
あるところまで順調なペースで行っている人は、何らかの変化によってそのペースが破られたときに、じゃあどうするのかと、そこで考えることになります。
でも、本当はそうなる前に、将来を考えてみることも必要だと思います。
(3)ただ流されていくのではなく、自ら流れを生み出すようなキャリアの構築の方法はあるのか
田村:流されるだけではなく、自ら流れを生み出す術はあると思っています。しかし、私自身、それを学ぶのに時間がかかりました。トランジション(キャリアの移行期)のタイミングで明確な選択肢も方向性もなく迷っていたとしても、やれることがあると思います。
その術とは、今日のテーマ「ビジョンとリアリティの両感覚を磨く」ことの背景にある考えです。それは、「根底にある構造が流れを決める」ということです。それを「構造力学」あるいは「構造思考」と呼びます。
-・根底にある構造がすべての流れを決める.jpg)
(4)流れを決定する構造を決めることができる
田村:皆さん、徳川家康の利根川改修についてご存じでしょうか? 利根川は大雨の時に放っておくと氾濫して、江戸中が水浸しになってしまう。では、利根川の流れを変える明確なビジョンは?それは単なる治水工事ではなく、どうやって江戸の町を豊かにするか、どうやって江戸が攻められない平和な町にするか。そうした周到な計画と明確なビジョンを持って利根川を変えていったんです。 皆さんのキャリアが川の流れのように流れていくとすると、その流れを決定する構造を決めることができるということです。
(5)構造を変えていくと、そこにテンションが生まれる
田村:構造を整えていくと、そこに「テンション」が生まれるというのが”緊張構造”という概念です。 わかりやすく言うと、ビジョンつまり自分の行きたいところがある一方、リアリティつまり自分の今いるところがあり、その間にテンションを生み出します。 それを私は「構造的なテンション=緊張構造」と翻訳しました。 この「構造的なテンション」という考え方を体系化したロバート・フリッツは、「物事が前進していくとき、上手くいくときの構造の一種」だと定義しました。MITのピーター・センゲが提唱したシステム思考や学習する組織における「クリエイティブテンション」も内実は同じです。ピーター・センゲはロバート・フリッツに構造思考を学んで、それを自らのシステムダイナミクス、システム思考に活かしました。
(6)それに向かおうとするエネルギーが生まれる
田村:ちょうど私達が自分のキャリアの中で今どこにいて、どこに行きたいのかが分かれば、自然にやり方が姿を現します。 目標と現状の間のギャップ、そこにエネルギーが生じるのです。 ちょうど弓に矢をつがえた時に狙った的に向かおうとするエネルギーが生じるように、皆さんがもしビジョンを描いてそれが本当に自分の欲するもので、そのビジョンに到達していない今の自分の立ち位置がわかったら、そこに向かおうとするエネルギーが生まれます。 このエネルギーのことを「構造的なテンション」と呼びます。

(7)現実の生活の中に、ビジョンの兆しやヒントがある
田村:5年後、10年後、15年後、20年後あるいは人生全体を描いていくときに、自分はどこに行きたいでしょうか?そして、今、どこにいるのでしょうか?考えてみてください。
私の場合は、さきほどお話ししたように、長らく迷走の中にいて、それが無駄な時間だったわけではありませんでした。 よくわからないながらも、テクノロジーが好きで、技術によって何かできるということが面白いと思ってやっていた。ところがひょんなことから失業して、新しい仕事のオファーがあって、それをやってみたら、これがまさに長く続けることができる仕事だったんです。
有名な2005年のスティーブジョブズのスタンフォード大学でのスピーチにも「振り返ったときに点と点を結んで線にできるけれども、将来に向かって点と点を線にすることはできない」という言葉があります。 その時点では明確なビジョンを描くことは難しくても、現実の中にビジョンの兆しがあったり、ヒントがあったりするのです。
ですから、キャリアの早い段階である10代や20代の時に「こっちに進む」というものが見つかった人はラッキーだと思いますが、30代40代のとき、あるいは50代60代になって、こっちに進みたいんだというものが見つかったら、それが今までの人生やキャリアの中におけるいろいろな経験や知見や蓄積がテンションとなって後押ししてくれるんです。キャリアデザインに緊張構造をどう活用することができるか。それを今日皆さんが考えるきっかけにできればと思います。
4.パネルディスカッション
~キャリアのこれから研究所のプロデューサー酒井氏の進行のもと、田村氏、森山氏、水野を交えて~

※左から、キャリアのこれから研究所のプロデューサー酒井章氏、
ロバートフリッツコンサルティング チーフコンサルタント 田村洋一氏、
ロバートフリッツコンサルティング コンサルタント 森山千賀子氏、
キャリアのこれから研究所所長 水野みち
ロバートフリッツコンサルティング チーフコンサルタント 田村洋一氏、
ロバートフリッツコンサルティング コンサルタント 森山千賀子氏、
キャリアのこれから研究所所長 水野みち
酒井:今日はよろしくお願いいたします。私はキャリアこれから研究所の設立に関わり、現在プロデューサーという形で関わらせていただいています。ここからは、田村さんと一緒に構造コンサルタントとして活躍する森山さんにもご一緒いただきます。
最初に、田村さんは、この構造思考というものにどのような形で出逢われたんでしょうか?
田村:元々は学生時代に、MITのジェイ・フォレスターという人のアーバンダイナミクスやシステムダイナミクスなどの文献をリサーチしていた時に触れたのがきっかけでした。 システムダイナミクスの世界ではこのような有名な話があります。
政府が住宅問題を解決しようと思って、公的な資金を投入して安く家を建てる政策を導入して、貧しい人が安い家賃でそこに住めるようにする。そうすると、貧困を長引かせる、と言います。つまり、公的政策が貧困を長期化させるということが、システム的に分析されていたのです。
これは面白いと考え方だと思いました。お金や努力を使って政策を変えて問題解決しようとすると、逆に問題を悪化させるということが起こるのだと。そして、この考え方を使って色々な政策課題を分析しようとしたのです。その何年後かに、ジェイ・フォレスターの弟子の1人であるピーター・センゲという人が、システム思考というものを提唱しました。
システム的に考えることがいかに役立つかを実感しました。裏を返すと、システム的に考えないと、良い意図を持ってやったことが、企業や社会や世界を悪化させるかが分かったのです。
善意でも、悪化させるということがある。ではどうすればいいのか?そう思ったときにピーター・センゲの師匠であるロバート・フリッツの著作に出会いました。 それが、私が構造思考に触れた最初でした。 ロバート・フリッツの構造思考を学んでみると、単に「世界はこうなっている」だけではなく、「自分の会社をどうしたら良いのか」、「自分の人生をどうしたら良いのか」、「自分のキャリアをどうしたら良いのか」、という様々なテーマに対するヒントや方法に満ちていました。
森山:私達はここで2種類の構造のことを言っています。一つは「行きたいところに首尾よく行ける」という構造です。もう一つは「動機が正反対の方に向いてる場合」の構造です。 例えばダイエットをする時、痩せたいとか、健康になるために、こういう体になりたいと思っているのに、一方で、たくさん食べてしまったり運動をしなかったりということがあります。思っていることとやっていることが反対の方に向いてます。 もっと健康になりたい、美しい体になりたいと思っているのに自滅的な行動をとってしまう。

この「正反対側に引っ張っり合う」ということが、構造的には「行きたいところに行けない」という状態の構造になるわけです。私の解釈で言うと、構造的に考えるということは長期的に考えるっていうことになります。例えば企業であっても、今年だけとか今月の売り上げや利益のことだけを考えると先の成長のための機会を逃してしまうということがありますね。そういう長期的な目線で計画をしてそれを実行していくということと短期的なものの間に葛藤が生まれます。
あるいは、皆さんのキャリアが最終的にどこに行きたいのか、ということになるのかもしれません。
酒井:ありがとうございます。 水野さんから見て、この構造思考というものをキャリアにどう生かしていけば良いと思いますか?
水野:そうですね。構造思考を少し頭に置くことによって、これは行きたいとこに本当に行けてるんだろうか、とか、自分のやってることは、揺り戻しが起こってるんじゃないかと振り返ることができます。ビジョンに対する自分のスタンスについて良い意味でクリティカルに吟味できるのではないかと思います。
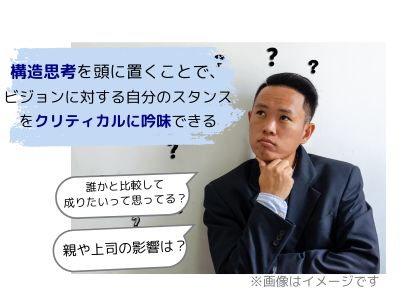
なにかを目指している時に、ふと「あれ?本当に自分はそうなりたかったんだっけ?」、「誰かと比較してなりたいと言っているだけかもしれない」「親が、上司が、良いと言っているからそんな気になってしまっていたのかも?」と疑問に思うこと。そして、構造として見た際にも、揺り戻しや停滞が起こっていたら、それは自分が望むことは何だろうか?この手段は合っているのだろうか?と問い直すことにつながります。
ビジョンが自分のものになっているかどうかは、自然に達成したいと思えるかどうか、つまり緊張構造が起こっているかどうかで確認することが出来るのという考え方です。私たちのキャリアの研修では、ワクワクしますか?という投げかけをしたりします。自分も最初はビジョンが描けませんでしたが、問いを持ち続けることで、日々の生活の中において見えてくることがあります。
もう一つ、私が構造思考ですごく好きなのは、「現実をしっかりと見る」ことで緊張が生まれるという考え方です。両方があってこそストレッチが利く。現実を見ないと、適切な行動が生まれません。私は昔、実現したいビジョンがあったのですが、権威者の方から「それはできない、100%無理だよ」と言われました。すごく落ち込み、腹が立ちました。「あなたには条件が揃っていない」と言われたのです。普通の人なら諦めたと思うのですが、別の人に「その条件がないのは仕方がない(現実の受け入れ)。でも、無理かは分からない。別の条件で出来るだけ努力してみたら?」と言われました。この発想は、現実を直視したからこそ、思いつくことができました。結果、別の強みでがんばり、100%無理だと言われたことが実現できたのです。(田村氏:すばらしい!)
周りから「あなたでは無理」と思われていることが分かったので、戦略を立てることが出来たのです。現実を突きつけられたからこそ、結果的にはそこに緊張構造が生まれたのです。もし現実から目をそらすような助言だけだったらのんびり望んでしまったかもしれません。自分にとっては、現実を見ることの重要性に緊張構造の素晴らしいヒントがあるなと思いました。

酒井:田村さん、パネルの最後に改めて「構造思考」についてお話しいただけますか?
田村:ピーター・センゲをはじめとするシステム思考家の人たちは、世界をシステムと捉えて食糧問題やエネルギー問題、気候変動の問題を解決しようと世界中で活動しています。しかし、皮肉なことにシステム思考は1970年代から活動しているけれども、世界を良くしたというのは非常に限られた例なのです。では、無駄なことをやっているか、というとそんなことはありません。 その過程で世界について学び、成長した人たちがそれぞれの持ち場でいろいろなやりたいことをやっている。 これがシステム思考の成果だと思います。一方で、構造思考は世界全体をシステムとして見るのではなく、自分の人生、自分のキャリア、自分のプロジェクト、自分の会社、チーム、これをどのように作り変えていくかに長けた方法です。
構造思考によって徳川家康が利根川の流れを変えたように、根底にある構造を変えてしまえば、成功したことが更なる成功を呼び失敗したことも学びになって成功の元になります。つまり、構造の転換が自分の足元から仕事や生活を変えていくことに繋がるのです。
5.参加者の皆さまからのお話と田村氏、森山氏のコメント
参加者の皆さん同士のブレークアウトセッションが終了後、数名の方がグループで出たお話を共有し、それに対して、田村氏、森山氏がコメントをくださいました。
(1)緊張構造が働いているか、テンションが張られているかどうか、の違い
●イベント参加者Kさんからの質問
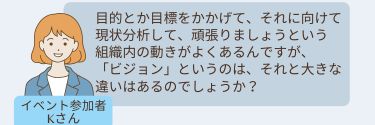
田村:特別に緊張構造とか構造思考と言わなくても、目標を記述して、現状分析して、そこにギャップを発見し、それをどうやって埋めるのかという計画を書いて実行する。これはもう世界中でよく知られた計画、実行の方法ですよね。
そういったやり方と、今いる所から行きたい所に行こうとするテンションが生まれた状態と何が違うのかというご質問ですね。
これは、テンションがあるかどうかの違いです。 現状を把握して立てた目標に向かって行きたいというエネルギーが生じていれば、それはとりもなおさず緊張構造です。 矢に弓をつがえて引き絞ったときに、矢がそこへ行こうとしている。このエネルギーがあるということです。例えばコーチングやカウンセリングをしていて目標を明確にしたら、もう矢も盾もたまらずすぐやろうというふうになることもあるとは思います。一方で、よくあるギャップ分析では、とにかくギャップを埋めなきゃいけないという気持ちになる。これは緊張構造が働いていない、テンションがはられていない状態です。要はこのテンションが生まれているかどうかなのです。
(2)ピアノが弾けるようになりたいエネルギーが生じている
田村:つい最近、こんな話がありました。友人の40代の女性がピアノでこの曲を弾きたいけれど、まだ弾けない。でもこの曲を弾きたいと思うと毎日時間を見つけては練習するんです。
なぜ練習をするのか?練習が楽しいからというよりも、「弾けるようになりたい」というエネルギーが生じているからです。こういうことは、芸術やスポーツの世界では普通ですが、意外とビジネスの世界だと違う。それはなぜでしょうか。
私は7年ぐらい前からサッカー始めたんですが、プロでもアマチュアでも、練習や試合はものすごく苦しい、苦しいけれどもゴールを決めたい、試合に勝ちたいっていう目標があったときに、絶対に手を抜く選手はいないんです。 それは、テンションが張られてるので、そこに行こうとするエネルギーが自然に揃うし、チームでテンションが共有されていればチームで足並みを揃えて、その目標に向かうんです。
しかし、残念ながらこういう状態になっている会社、企業・職業集団は稀です。 巧妙なデザインと努力と運によるもので、放っておくとそうはならない。個人のキャリア目標でも、「これをやりたい」と言っても本当にやりたいことかどうかわからないために、人は努力や工夫ができないんです。 怠け者だからできないのではなくて、テンション、構造的にその努力や工夫やあるいは才能をそこに注ぎ込むということになっていないからなんです。それが違いです。
(3)テンションがあるか、ないか。構造的に前に進む構造になっているか
田村:「テンションがあるのかないのか」が前に進むために必要な構造です。ただ、、「一時的にテンションがあっても、また逆戻りしてしまう」ということもあり得ます。 これは継続的に前に進む構造になっていないために起こることです。 一時的にめざす目標があっても、それとは違う目標があると違う方へ行ってしまうのです。 これはリバウンドするダイエットみたいなもので、痩せたいと思うけれども、目標に近づけば近づくほど「まぁいいだろう」と思ってまた食べてしまう。 目標に近づけば近づくほど、このぐらいでいいかなと思って緩んでしまう。人から与えられた目標や世間から与えられた目標の場合、「このぐらい頑張ったんだから少し休んでもいいかな」と緩んでしまう。これが従来の問題解決的な方法と構造アプローチによる創造的な方法の決定的な違いですね。
(4)今どこにいて、どこに行こうとしているのかを明確に持ち続ける
田村:組織の場合は、サッカーのようなスポーツと違って会議にしてもプロジェクトにしても、「みんなでここに行くぞ」というゴールのようなものが共有されていないですよね。言葉では共有されていても、本当にみんながそこに行きたいとは限らない。仮にビジョンが共有されている場合でも、今どこにいるのかということが共有されていない。 そうするとテンションを維持できない。 一見できたように思えても、バラバラになってしまう。ですから、「今どこにいて、どこに行こうとしてるのか」を明確に持ち続けることが必要です。 これがテンションの張られた緊張構造だということです。
(5)やればやるほどもっとやりたくなってくる
●イベント参加者Yさんからの質問
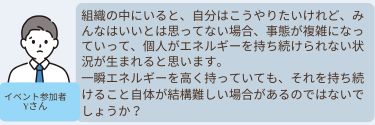
田村:問題解決のエネルギーと創造的なプロセスのエネルギーは全く違うところから出てきます。 例えば部屋が散らかっていてこれを片付けなきゃならない、片付けろと言われたので端から片付けなきゃならない。組織の仕事でも、この問題をモグラたたきのように片付けなきゃならない、そういう仕事をやっていると1日でエネルギーは消耗して、すっかりやる気がなくなってしまう。エネルギーがずっと落ちていく、 消耗していくんですね。
それに対して自分がどんな状態を作り出したいか、例えば片付けるにしても、「この部屋をどういう状態にするか」というビジョンがあって、それに対して今どうなっているかという現実があって、ここにテンションが生まれると、そのテンション自体、構造自体がエネルギーの供給源になるんですね。 やればやるほど、もっとやりたくなる。 サッカー選手が肉体の疲労はあったとしても、プレーすればするほどもっとプレーしたくなる。こういう経験を選手ならみんな持っていると思うんですね。
しかし、日常生活や仕事でその状態をつくることができないのは、自分が悪いんじゃなくて構造が間違ってるからです。 Yさんがおっしゃった通りで、エネルギーがキープできないのは自分が悪いのではないかと自分を責める必要はなく、 置かれている構造が悪いのです。ここに行きたい、 今ここにいる。これが明確に共有されていれば、力を注ぐとこと自体が、更なるエネルギーを生んでいきます。
例えば、一日中創造的な仕事をしていると、家に帰ったときに、むしろ元気になっているご経験が皆さんにもあると思います。もちろん肉体的な疲労はありますが、マインドは作り出せば作り出すほど、もっと作り出したくなる。これは音楽をやる人とかスポーツやる人とかに限られたことではなく、仕事をやる人も、「これを作り出したい」という構造を維持することができれば、そこからエネルギーが生まれるということです。これは問題解決ばかりしているとエネルギーがどんどん消耗していくのとは対照的ですね。
(6)フェードアウトしてしまうこと、長く続けること、構造の違いからくる
森山:何かを始めたときはエネルギーがあるのに、その後フェードアウトしてしまうのには理由があります。やりたいと思ったことは長く続けることができる、という経験は誰でもあると思います。 これが「構造」とそうではないものとの違いなのです。
続かない時というのは、例えば会社で目標や数字が与えられて「やらなきゃ」とは思うけれど、達成したからといって自分にとってどんな価値があるのかな、という気持ちになる。つまり、本当に自分が欲しいものなのかどうかがわかっていることが大切です。そして、今はどうなのかというリアリテイを持って客観的に見ることが良い構造を作るポイントです。
(7)キャリア全体を想像的なプロセスにしていくことは可能
田村:一言だけ補足すると会社の仕事の場合は、ベストな状態とそうじゃない状態があります。 ベストの場合は、会社がやろうとしていることと、自分がやりたいことのフェーズが揃っている状態。そうすると、自分がやりたいことを会社が後押ししてくれて、会社がやりたいことを自分がサポートすることができます。これがベストだと思いますが、そうじゃないことも多いですよね。自分がやりたいこととは関係なく、会社の目標や上司の指示によってやらないわけにいかない。それが、自分の任務ですからね。要はそれをやるために雇われてるわけなのです。じゃあ、なんでそこで雇われてるか。その会社の仕事で収入を得てキャリアを築いて、やがてこっちに行くっていう大きな目標や自分の進路価値や志と結びついて、そのための手段として日々の仕事をやっているということです。
ですから、ベストな状態や恵まれた状態ではなくとも、自分の力を使って目標を達成し、成果を出すことによって自分の大きな目標に繋がっていく。そのように思えれば多少消耗したとしても、キャリア全体を創造的なプロセスにしていくことは可能だと思います。
私自身のキャリアの前半は、正にそれでした。後半はもうベストな状態、自分と周りの人が同じ方向を向いて力を合わせて知恵を集めて仕事をしている。でもそうじゃない状態でも創造的なプロセスは可能だということです。
水野:ありがとうございます。皆さんぜひ新たな1年に向けて、ビジョンとリアリティをこんな視点で見直してみてください。まず、ビジョンとリアリティの緊張構造になっているか。本当に望むビジョンになっているのか。もし揺り戻しが起こってるとしたらまたは、それが達成できないとか、なんだかやる気がないとしたら、そこに向かう価値が他人事になっている、本当には願っていない可能性があるということです。その際には、改めて本当に願うものは何かを考えてみるタイミングだということを教えて頂きました。 とはいえ、すぐにビジョンにたどり着けない人もいる。田村さんの前半の人生は多くの人が共感するものだったのではないでしょうか。
私も迷いの中、キャリアをうろうろすることがあります。しかし、経験の中にビジョンが見つかる場合もあるということを教えて頂きました。1回ビジョンを仮に立てて動いてみる。 そして違うなと、思ったり、失敗したり、行き詰ったり、揺らいだ時に、その経験と向き合うことでビジョンが見つかってくる。 ぜひ構造という言葉を念頭に、自分の心の弦はピンと張っているのかどうか意識しながら深めていただければと思います。 例えば明日から、明日はどんな1日にしたいのかなとか、明日から緊張構造を試しながら1日を生きてみるっていうことも、今日のお持ち帰りいただけるヒントじゃないかなと思いました。
(8)明日からできること
1日のビジョンとリアリティを見直す
1)構造になっているか?ビジョンとリアリティの緊張構造
2)揺り戻しが起こっているとしたら、改めて本当に願うものは何かを考えてみる。特にリアリティ(現実・経験)の中にビジョンが見つかる
1)構造になっているか?ビジョンとリアリティの緊張構造
2)揺り戻しが起こっているとしたら、改めて本当に願うものは何かを考えてみる。特にリアリティ(現実・経験)の中にビジョンが見つかる
6. 最後のひとこと
●短い創造プロセスを毎日実践してみる~皿洗い時代の経験~
田村:水野さん、素晴らしいまとめをありがとうございます。 まさにその通りですね。明日どんな1日にしたいのか、自問してみる。これいいですね。私が実際に仕事に悩んでいた時にやっていたことを一つ最後に紹介したいと思います。
~1日よりもっと短い創造プロセスを毎日実践してみる~
1997年当時、私がやっていた創造プロセスが何だったかをご紹介します。日中の仕事がやることなすこと上手くいかなくて消耗していた時です。私は、皿洗いに創造プロセスを見出しました。皿洗いは、毎日のこと。汚れた皿を見たときに、ただ、問題解決するのではなく、これが全部綺麗になっている、というビジョンを頭の中で描きました。 ロバート・フリッツに学んだ方法ですが、描いてテンションを感じて、それから洗うんです。そして、皿洗いの場合は、ほとんど必ずビジョンに達成できます。 達成したら「頭の中に描いたビジョンを達成したぞ」と満足して次に行くんです。 この「小さな練習をする」っていうのはとてもいいですね。 リフレッシュされる経験になります。
1997年当時、私がやっていた創造プロセスが何だったかをご紹介します。日中の仕事がやることなすこと上手くいかなくて消耗していた時です。私は、皿洗いに創造プロセスを見出しました。皿洗いは、毎日のこと。汚れた皿を見たときに、ただ、問題解決するのではなく、これが全部綺麗になっている、というビジョンを頭の中で描きました。 ロバート・フリッツに学んだ方法ですが、描いてテンションを感じて、それから洗うんです。そして、皿洗いの場合は、ほとんど必ずビジョンに達成できます。 達成したら「頭の中に描いたビジョンを達成したぞ」と満足して次に行くんです。 この「小さな練習をする」っていうのはとてもいいですね。 リフレッシュされる経験になります。
水野:ありがとうございます。今回ビジョンとリアリティというテーマでお届けしました。皆さまいかがでしたでしょうか? 次回は来年。また9つのテーゼのイベントもお届けしたいといきたいと思います。 本日はありがとうございました。 田村さん、森山さん、皆さま、貴重なお話や問いをありがとうございました。
プロモーションイベントの運営・実務を担当。趣味は読書といけばな。最近、涙もろいのが悩みです。
この記事はいかがでしたか?
ボタンをクリックして、ぜひご感想をお聞かせください!
シェアはこちら
RECOMMENDED関連おすすめ記事
人気記事
-
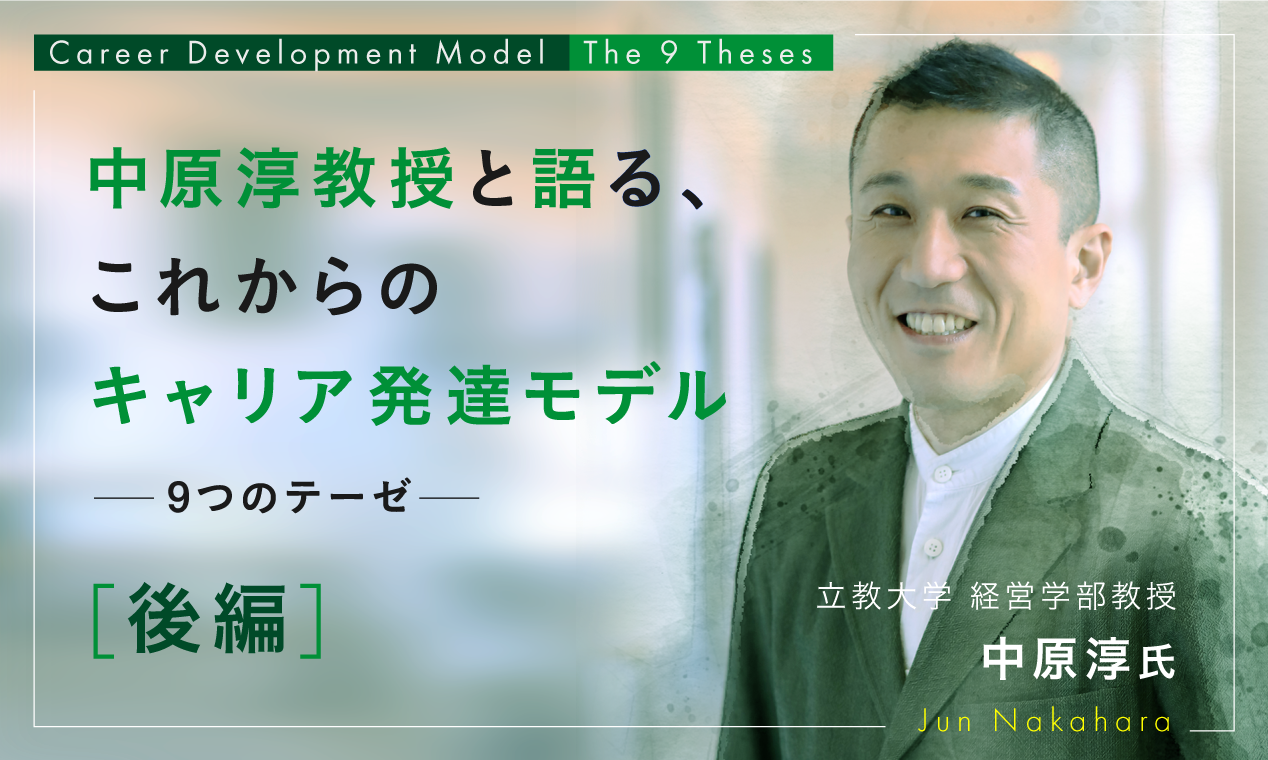
PICK UP
イベント
【後編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.8.29
-
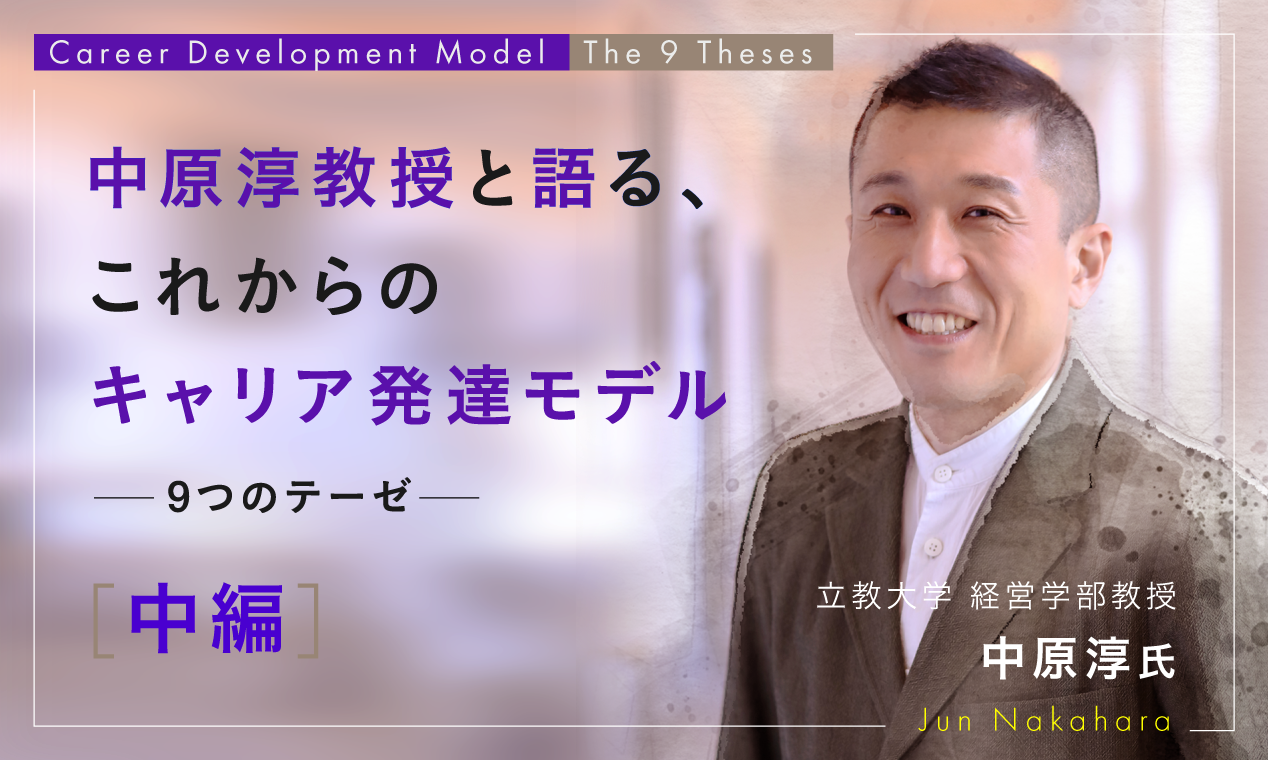
PICK UP
イベント
【中編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.22
-
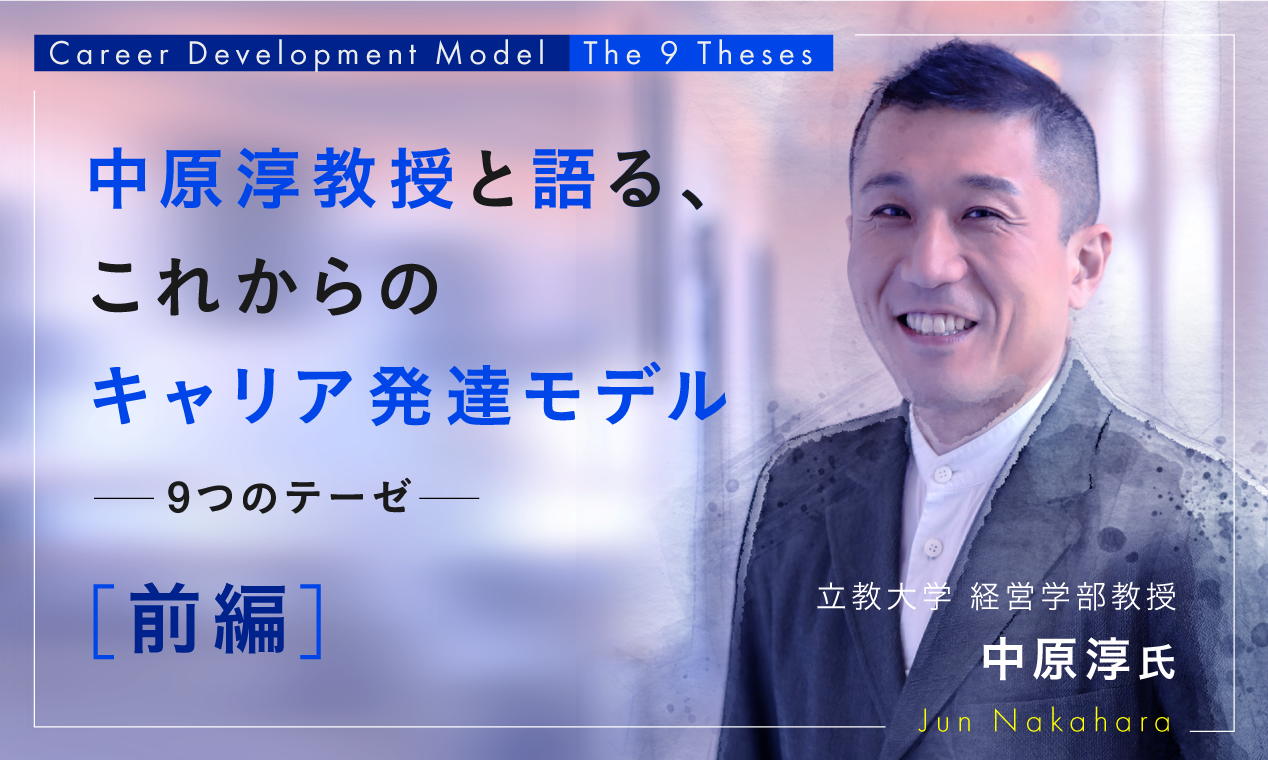
PICK UP
イベント
【前編】中原淳教授と語るこれからのキャリア発達モデル~9つのテーゼ~
2022.4.19
-
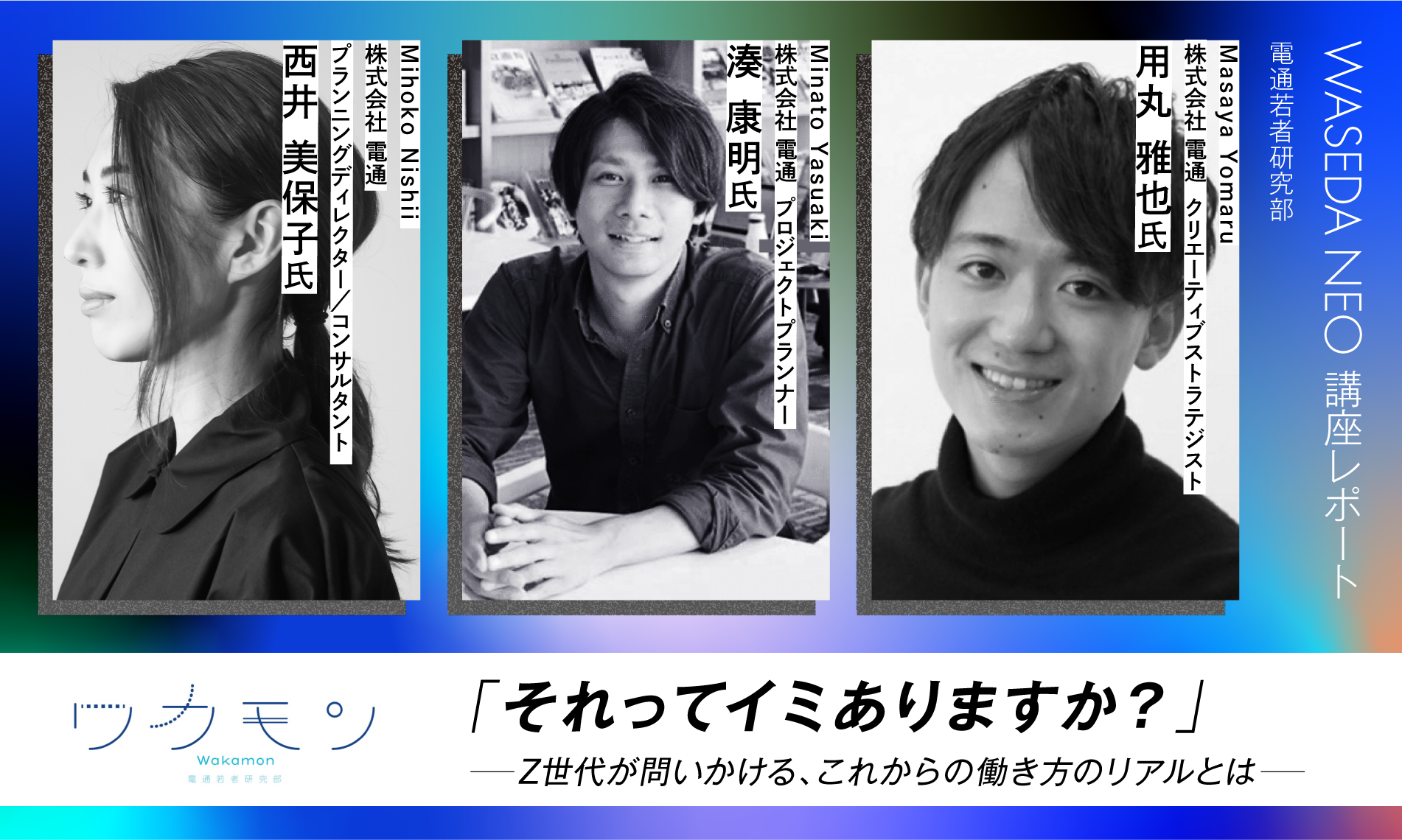
イベント
「それってイミありますか?」 -Z世代が問いかける、これからの働き方のリアルとは-
2022.2.8
-

PICK UP
特集記事
ひとり一人には役割がある。アーティスト・小松美羽氏が語る言葉と“これからのキャリア”の重なり
2020.12.28
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(後編)
2020.12.4
-

インタビュー
個人
マーク・サビカス博士「コロナ禍におけるキャリア支援」 オンラインインタビュー(前編)
2020.10.30